コンパス社員がお届けする最新情報ブログ

ストレスに対する詳しい知識
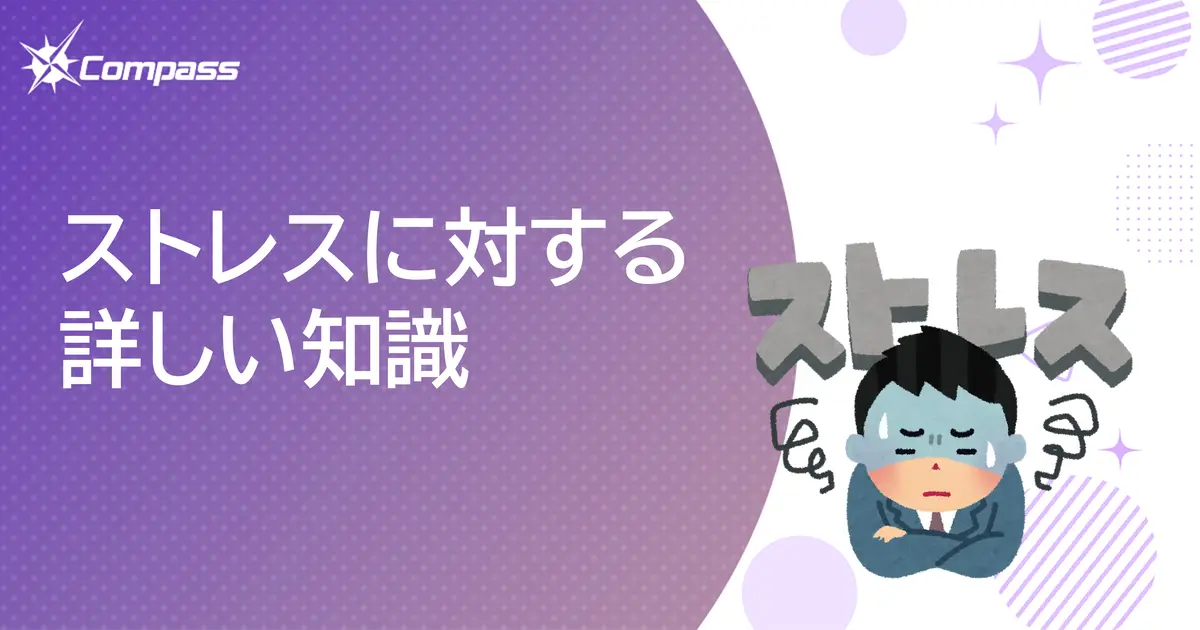
自己紹介
こんにちは。コンパス株式会社の小林です。
幹部及び人材戦略部の部長を担っております。
人材戦略部は”人材採用チーム”と”人材サポートチーム”という2つのチームから成っている部署であり、
2023年の3月に私が入社したと共に立ち上げられた部署となっております。
”『熱しやすく冷めやすい』私が、10年続けられていること”というタイトルの記事を書いた篠塚が
4月に入社して採用チームを作り上げていき、私は人材サポートチームを作り上げてきました。
2名だけだった人材戦略部は現在メンバーも増え、
私は両チームを管理する部長として動いていますが、
ルーツとしては人材サポートチームとなりますので、
今回こちらの記事では人材サポートチームがメインで行っている、
社員のメンタルケアやヒアリング/カウンセリングに紐づき
”ストレス”という物にフォーカスを当てた記事をお送りしたいと思います。
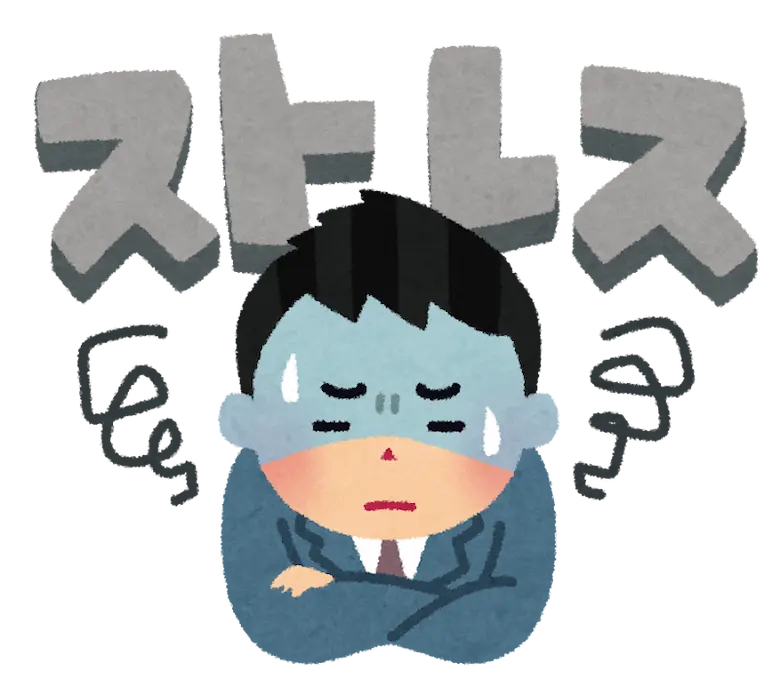
①ストレスとは
ストレスとは、「外部からの刺激によって心や体に負担がかかり、緊張状態になる事」を指します。
つまり、人が環境や状況の変化に適応しようとする際に感じる、心理的・生理的な反応の事です。
ストレスの原因(外部からの刺激)となる物を”ストレッサー”
ストレッサーに対する抵抗の結果として現れる物を”ストレス反応”と呼びます。
風船を使った例を挙げてみると、以下の通りとなります。
—
風船=自分の心と体
空気=ストレッサー(ストレスの原因)
—
ストレッサー(空気)が増えると、風船はどんどん膨らんでいきます。
少しなら問題ありませんが、入れすぎると風船は破裂してしまいます。
また、吹き入れ口を摘まんでいないと空気は漏れていき元の形に戻ろうとします。
これはストレスの無い状態に戻ろうとしているという事であり、この作用がストレス反応となります。
②ストレスによる身体の反応
ストレッサーの出現から生じるストレス反応によって人間の身体には様々な変化が起きます。
ストレス反応の影響は筋肉、骨格、内臓、神経、血管など
多岐に渡る事が生理心理学という分野で研究されており判明しています。
③ストレッサーの種類
ストレッサーの種類は代表的な物として以下の4つに分類されて表される事が多いです。
物理的ストレッサー:
寒冷、騒音、振動、光、熱、満員電車など、環境や物理的な刺激による物.
化学的ストレッサー:
化学物質、薬物、公害物質、タバコ、アルコールなど、化学物質による物.
生物的ストレッサー:
感染症、炎症、病原体、花粉、アレルギーなど、生物由来の刺激による物.
心理的ストレッサー:
仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来の不安、経済的問題、怒り悲しみなど、精神的な刺激による物.
これらを見てどうでしょう?ストレスという言葉から連想された事柄は、
心理的ストレッサーに分類される物が多かったのではないでしょうか?
ただ、ストレスという物は日々の何気ない生活の中で様々な物からもたらされ常に付きまといます。
ストレスと上手に付き合っていく為には対処法を心得ておく事が非常に大切ですので、
後ほど対処法についても記載したいと思います。
④ストレッサーに対する反応
ストレッサーに対する反応には警告期、抵抗期、疲憊期という3段階があると言われており、
・ストレッサーにさらされた直後の、一時的に抵抗力が低下する時期を警告期
・ストレッサーに対抗しよう適応しようとして抵抗力が上がる段階を抵抗期
・ストレッサーが長期間継続し、身体が限界に達して再び抵抗力が低下する段階を疲憊期
となります。
人間の生理的機能は警告期、抵抗期、疲憊期という順に
段階を経て変化するとされており、これを汎適応症候群と呼びます。
汎適応症候群は病気ではありません。
ただし、この状態が長期間続く(疲憊期が長期間継続する)と、
身体の抵抗力が低下し続け、病気のリスクが高まったり、
様々な疾患を発症する可能性は出てきてしまいます。
⑤ストレッサーへの対処法
ストレッサーへの対処法として言える事はとてもシンプルで、
『原因を特定し適切な対策を講じる事』です。
例えば、ストレス=睡眠不足の場合、寝れないという事がストレッサーとなります。
なぜ寝れないんだろう?等から原因の特定を行う事がまず必要であり、
十分な睡眠をとる為の適切な対策を講じなければいつまでも対処されず、
ストレスにさらされ続ける事になってしまいます。
「バランスの取れた食事をする」、「適度な運動をする」、
「リラックスできる時間を作る」、「相談できる相手を見つける」等、
自分に合った方法を特定して適切な対策をしていきましょう。
まとめ
ストレスに晒され続けると④ストレッサーに対する反応でも記載した通り、
病気のリスクが高まったり、様々な疾患を発症する可能性があると述べました。
身体のどこにどのような症状が現れるのかは個人差がありますが、
例えばストレス反応の結果が胃に強く影響した場合は胃潰瘍となる可能性が出てきてしまったり、
呼吸器系(肺など)に強く影響した場合は過換気症候群となる可能性があったりします。
改めてですが、ストレスをそのままにしたり、目を背けたり逃げたりをしていては、
一向に改善される事はありません。
”嫌だな”というストレスに遭遇した際、もちろん全てがそうとは言い切れませんが、
身を引いたり逃げれば解決するわではないと私は思います。
一旦は収まる事はあるかもしれませんが、また同じ状況になった際には
同様のストレスがかかってくる事になります。
こちらの記事を読んで少しでも意識を向けていただければ幸いです。
ありがとうございました!
豆知識
『ストレスは全て悪いものなのか?』
ここまでストレスについてやそれによる影響をお伝えしてきましたので、
ストレス=「悪い物」というイメージになっているかと思います。
ただ、例えばジェットコースターに乗ると緊張・不安・恐怖などが発生し、
結果として人間の身体には生理的変化が起きます。
つまり、ジェットコースターはストレッサーであると言えます。
しかし、ジェットコースターによって引き起こされるストレス反応は、
ジェットコースターから降りればすぐに無くなるので、
病気になってしまうというケースは少ないのではないでしょうか?
むしろ、このようなストレッサーがもたらすストレス反応は、
快感を引き起こす場合が多いと思います。
この事からストレスは良い・悪いという観点よりも、
程度の問題として、少なすぎるか、適切か、過剰か
という観点から述べるのが正しいとされています。
ストレッサーの程度は人間が実施する課題(活動)の困難さと関係しており、
単純にストレッサーが弱ければ課題(活動)が効率的にできるという事ではなく、
課題(活動)の状況に応じて、適度なストレッサーがあるという事が言える事です。








